
この記事は【母】が書いています
2019年5月のことです。
私は叔父の家を訪問しました。
会うのは数年振りだったので、我が家の近況報告として、
- 息子が長年不登校だったこと
- その息子が今は元気に大学に通っていること
- 将来は研究職、教授職を目指していること
といったことをざっくばらんに話しをしたのです。
私が不登校のことを話したからなんでしょうね。。。
実は・・・
「次女の小学生の娘が不登校で・・・」
と俯き加減に叔母が話を切り出してきました。
とても心配そうな表情でしたね😞
叔父、叔母の気持ちは、とてもよくわかります。
そして、年が明けた2020年元旦。
叔父と叔母からの年賀状には
「孫が通えるようになりました!」
と嬉しい報告が!
「良かったなぁ」という思い。
「このまま通い続けてくれればいいなぁ」という思いもあって、みんなが笑顔で応援している姿を想像しておりました。
身近なところにもある不登校、決して人ごとではありません。
私の不登校の経験がそうさせるのか、その時の私は叔父叔母の心配、不安が手に取るようにわかりました。
叔父叔母の性格もある程度はわかっているし、家庭環境もイメージできるので、理解しやすかったというのはあります。
こうしていけば変化していくかも?というのも見えていました。
私がお役に立てるかどうかは別として(笑)、叔父叔母には励ましの手紙を送り、あとは登校できるかどうかではなく、家族関係が良好になっていくことを願っていたのです。
小学生の不登校は私も経験しましたが、当時の私は当事者です。
今回は、親戚とはいえ、外部、第三者的な立ち位置。
当事者では見えないことが、よく見えるものですね。
当事者だった時は自分のことを客観的に見れるわけがなく、ただただ自分の枠の中で正解を探し求めるということをしていました。
それは、その心の奥には、
「誰にも知られずに解決したい」
という想いが潜んでいたからなんですよね。
不登校はそれだけ人に言えない悩みなのです。
今の私なら当時の私に、
「こうすればいいのに・・・」
と思うことはたくさんあります。
現在小学生のお子さんの不登校で悩んでいる方から見たら「ふざけたことを言わないで!」と思われるのかもしれないのですが、でも、私はそう思うのです。
あくまで私の考えになりますが、小学生の不登校について書いていきます。
小学生の不登校は子供の心を守るだけでいい
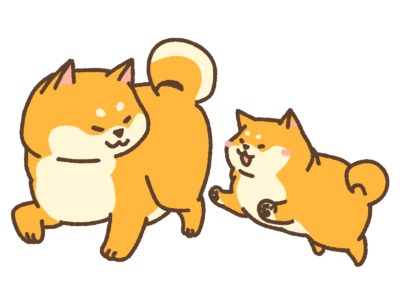
小学生の子供はまだまだ自分の思いを言葉で表現できないことが多いですよね。
不登校の理由となると、中学生でも、高校生でも明確に答えられる子は多くはないと私は思っています。
登校することに何かブレーキがあるのは確か。
でも、それが何であるかをわからないことも多いのです。
そして、子供が話してくれる登校できない理由というのは、真の答えである可能性は低いですね。
そう思っていた方が良いと思います。
親に聞かれるから、答えなきゃと子供は思う。
そして、
「◯◯くん(ちゃん)に◯◯された」
「◯◯先生に◯◯と言われた」
と表面的な対処可能な答えをする。
↑
私の息子がそうでした。
それが原因であることも確かなのですが、本当の原因はもっと深いところにあります。
これは会話のきっかけ作りくらいに思って、子供の心を安心させることの方が大事です。
私はこれができていなかったので、ここがある意味ポイントだと思いますね。
「そうだったんだ。。」
「辛かったよね。。」
「気づいてあげられなくてごめんね。。」
と、子供の心の氷を溶かしていく。
もしかしたら、これだけで小学生の子供さんなら不登校が改善していくかもしれないと私は思っていて、私にもし小学生の不登校の子供(孫にしましょうか😂)がいたら、まずはそうして様子をみることをするでしょう。
「うん、うん」
と話を聴きながら、その子の心の氷を溶かし、温めていく感じ。
温めていくというのは、その子がやる気になるようなそんな声がけとか、その子が笑顔になるようなことですね。
ここで認めてあげれば、自己肯定感が強い子供になるというのが私が思うことです。
不登校であることで否定されて育ってしまうと、それが潜在意識下に残ってしまいます。
こうした小さい頃の経験は自分でも気づかないうちにトラウマになってしまうことも多いですね。
実際、子供時代の経験で大人になってからも苦しめられたり、縛られている方もいるのではないでしょうか?
ですから、小学生の不登校はある意味幸運なのかもしれません。
ここでの対処次第で、その子は自信をつけることもできるし、のびのびと才能を伸ばしていけることもできますから。
目の前の「学校に行かせる」ということよりも、もっと先の子供の将来を考えて、心の傷を残さないようにしたいですね。
私はそう思っています。
小学生の不登校〜夫婦関係、親子関係は良好ですか?
小学生の子供の場合、学校の問題というより、夫婦関係、親子関係のことが多いようにも私は感じています。
それはいろいろなケースがあるでしょう。
- 夫婦仲がよろしくなくて、お母さんが我慢ばかりしていたり、
- 親の子供への関心が薄くて、子供が寂しい思いをしていたり、
- おじいちゃん、おばあちゃんがお母さんにガミガミ言いすぎていたり、
- 悪いのはあなたと人のせいにばかりしていたり、
などなど、あげればキリがない(笑)

子供は何か不安なのではないでしょうか?
親に理解して欲しいと思っているのかもしれないし、励まして欲しいと願っているかもしれません。
子供を登校させたい気持ちはよくわかりますよ。
私も子供の気持ちよりも、とにかく通わせることに必死でしたからね。
ただ悲しいことに、親からの話が「通わせる」方向にばかり向いてしまうと、残念ながら「通わない」現象がますます強くなってしまいます。
親の一方的な抑圧のエネルギーが子供に流れているだけですから、言葉は悪いですが、これでは子供を操作していることと同じです。
これでは、子供は辛いですよ。逃げますよ。
ですから、小学生のお子さんが不登校なら、まずは自分の心配、不安よりも、子供を安心させてあげて欲しいな、と私は願います。
誰か一人でもそういう目でみる方がいれば、子供の心は救われます。
それが母親なら一番理想ですけどね😊
誰か一人が理解をしてあげれば、それは徐々に波紋のように広がる
叔父と叔母もお孫さんの不登校で辛かったんだと思います。
思いを吐き出せるのも叔父叔母の夫婦間のみで、なかなか外で話すことはできなかったのではないかと想像しています。
はい、不登校とはそういうものですから。
まだまだ世間の目が冷たい、ということですね。
私はその後、ただただ思いを伝えたくて、
「◯◯ちゃんのお子さんだから、おじさん、おばさんのお孫さんだから、絶対大丈夫」
「理解してくれる大人の存在があると子供は救われる。それが、おじいちゃん、おばあちゃんならお孫さんは幸せ」
「信じて、見守ってあげていただけたら嬉しい」
というような内容の手紙を送ったんですね。

おじいちゃん、おばあちゃんの家が明るく、軽ければ、お孫さんはそこが安心の場所になるし、従姉妹も心が救われて元気になりますからね。
叔父叔母には、娘や孫が居るだけで、ホッとする、なぜか元気になれる、笑うことができる、そんな存在でいて欲しい、と勝手ながら祈っておりました。
よくあるのは、
「お前のしつけがなっていないから」
「甘やかすからそうなるんだ」
と言ってしまうパターン。
この対応は問題ですよね。
「お前が悪い」
で問題は解決するかというと、まず解決しない。
ついでに関係もこじれて悪化😅
小学生の子供が実際その場面を見ていなくても、母親の感情が揺れ動いているのは子供は感じ取りますよ。
そして、子供はお母さんの様子に不安になり、というループになりますよね。
人のせいにして問題が解決するかというと、そうではないですよね。
もし、それで解決できたように見えるのなら、それは相手の方が大人だったということ。
一人がこの過ちに気づけば、それはそこから波紋のように広がります。
わずかな広がりかもしれませんが、まずは一人が気づかないことには始まらないということ。
繰り返しますが、「通わせる」ことより「子供の心を守ること」。
小学生の不登校はこれだけでいい、というのが私の思うところです。




コメント